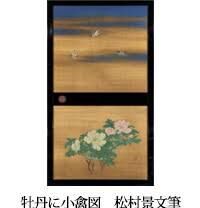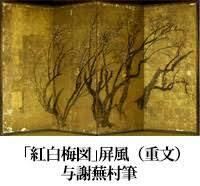扇の趣展
展覧会情報

開催期間
2020年9月15日 〜 2020年12月15日 まで
概要
扇は平安前期に、日本で創案されたといわれています。涼をとるという機能としては、中国伝来の団扇(うちわ)と変わりませんが、扇は折りたためることから、後世には、持つことが礼儀となり、祭事などにも用いられました。また茶道でも必携であり、舞踊にも欠かせぬ道具となっています。扇の形状が末広がりであることから、吉祥を示すものとして、扇面に和歌や絵を遺すことはもちろん、さまざまな工芸品に用いられました。たとえばお膳や食器、燭台、火鉢などに見られます。
なにより、めでたい宴席のしつらいには最適な形といえるでしょう。その実例が、重文角屋二階の「扇の間」に見られます。天井が、59面の書画の扇面で貼り交ぜられております。絵画には、岸駒(がんく)や長谷川雪旦、書蹟には歌人の香川景樹、本居大平などの作品があります。天井のみならず、欄間の障子や襖の引き手、燭台の台座、火鉢にも扇形が使われています。末広のしつらえによって、風流を尽くしてもてなしに努めていました。
本展では、書画の扇面や扇形の工芸品を展示しているなかで、主なものをここにご紹介いたします。